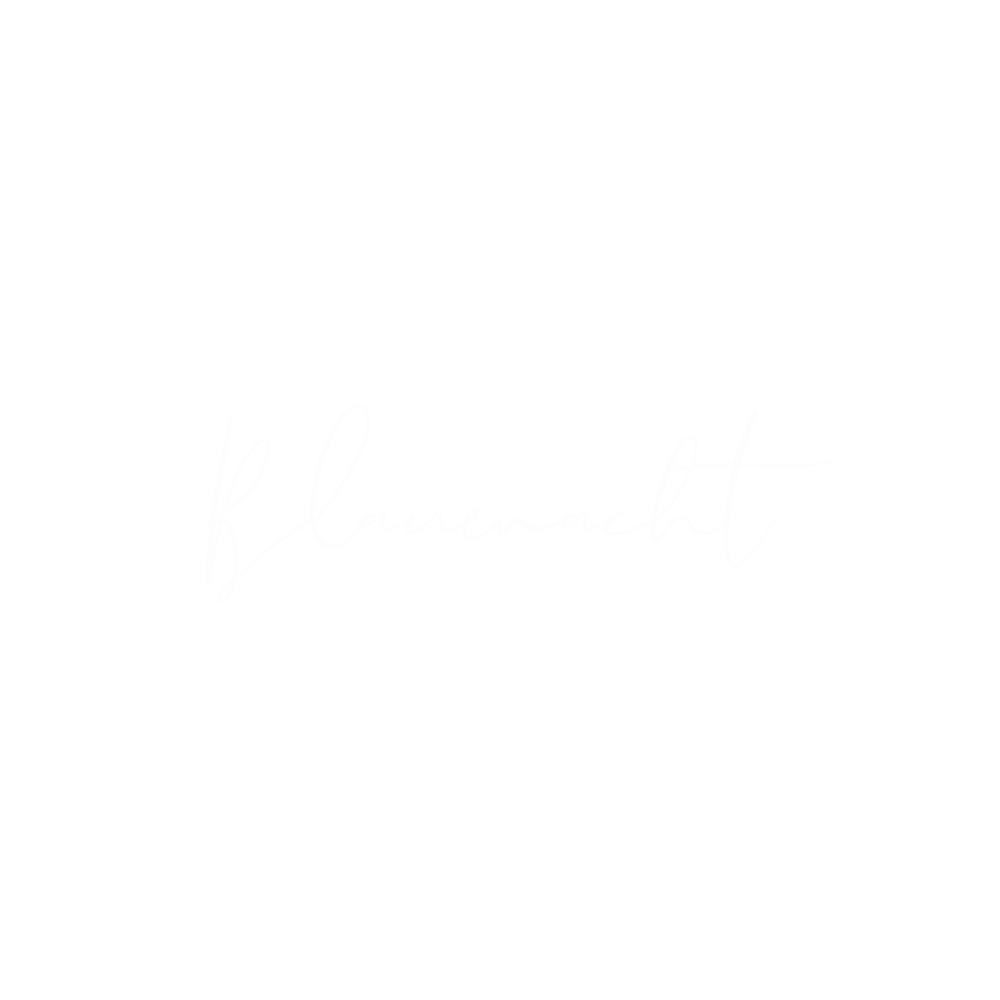Nessun Dorma
「Wanderkinder im Wunderland 終」の前提であり補足でありその後数年経って思い返した時のこと、みたいな話。
あるいは、カイザーと読書について。
カイザーが演劇はもちろん文学全般わかる人になっています(でも一番知識があるのはやはり演劇関係だと思います)。
数年後、と書きましたが、本当に数年経って関係と感情が落ち着いて愛情を自覚してないとこういう回想はしなそうです。
あんな男でも、一応は知識と経験を使って仕事をしていたらしい。あの家にはその知識の源流になった本がたくさんあった。あの女がいなくなってからは、それらは埃をかぶっているだけになっていたようだが、クリエイターとしてのプライドなのか何なのか、あの男は本を売り払うというようなことはしなかった。……尤も、本の背で殴られることはあったが。
仕草、台詞回し、目線、間合いの取り方。考えてみれば、「人を惹きつける」とか「人心を掴む」とか、そういうやりかたを最初に学んだのはあの時に読んだ本からだった。なるべく家にいないようにはしていたが、四六時中外に出ているわけにもいかない。できるだけあの男の目に留まらないよう、薄暗い自分の部屋で小さくなっていて、かといってそれだけで時間が進むわけでもない。そういう時に、乱雑に積み上げられたあの男の本を布団――といえば聞こえはいいが、まあ要は布だ――に持ち込んで、息を潜めて文字を追っていた。そうしていれば気配を殺していられたし、時間が経つのも早くなった。
あの男は演出家だったから、家にある本も自然と舞台に関わるものが多く、技巧やメソッドについての本はもちろん、戯曲やいわゆる名作と呼ばれる文学作品もたくさんあった。熱心だったのかただ集めていただけなのか、ゲーテやシラー、その他
――何にせよ、共感などなくても知識として理解することはできる。そして、人心を掌握するには理解があればよかった。
ただ、本を読むようになった発端や目的はどうあれ、読書は嫌いじゃない。知識を増やし、人を操る術を知るというのはもちろんあるが、自分が人間未満で……つまり人間になるには"何か"が欠けていることはわかっていたから、本を読むことでその"何か"を補う、もしくはそれらしく振る舞うことができるかもしれないと思ったし、自分の生きる世界とは別の世界、別の物語に触れるのは、そう、確かに楽しかった。その、別の物語というのが胸糞悪いということだって往々にしてあって、自分の生きてきた途を否応なく思い返してしまう時もあったが、その度に自分の生き様や怒りを新鮮に自覚
"あの時"、何も考えられない頭でするりと口をついて出たのがそれだった。あれほど共感などできないと失笑すらした『ロミオとジュリエット』の一説だったのは皮肉としか言いようがない。先に引用したのは名前だったからそれに釣られたと言えばそうだが、別に引用で返す必要があったわけでもないのに、気づけば口に出していた。
自身で考えることを、……自身の言葉で語ることを許されずに生きてきたあいつは、その分文学だとか歴史だとか、そういう知識で代弁することが多い。ふさわしい場面で、知的な会話ができる――そうなるべく育てられてきたのだから、これは当然ではある。自分の言葉を探すよりも簡単だったとか、ただ不意に浮かんだのがそれだったとか、いろいろと理由は思い当たるが、なぜあの時あいつが"Parting is such sweet sorrow"という一節を口に出したのか、実際のところはわからない。おそらく俺の推測は合っているのだから、別に敢えて理解したいとも思っていない――おそらく後者に違いないのだ。なぜって俺がそうだったし、あの時確かに俺たちは
いや、別に理由はどうでもいい。このことにしても何にしても、全く交わるはずのない者同士がこうやって何かを通して繋がるというのは不思議な気分だったし、今になって思い返してみれば、あれはきっと、確かに、よろこびだったのだろうと思う。全く違う二人の人間なのに、あの瞬間、熱も心も思っていることも確かに全部同じだった。そして持っている
生い立ちも、性格も何もかも違っていて、同じなのは互いに離れられない、互いに執着している、という部分と、知識だけ。心は見えないし、言葉は容易に嘘をつくのだから、知識――文学というのは、俺たち二人にとって目に見えて確かめ合うことのできる唯一の共通項と言ってもいいのかもしれない。
……なんて、そんなものはただ都合のいい解釈を当て嵌めただけだ。読書家なんていくらでもいるのだから、それを共通項として見出したからと言って特別感などありはしない。ありはしない、のに――そうやって、特別を見出そうとしてしまう。だからつまりはそういうことで、やはり俺たちは互いに離れられないし離すつもりもない。
そう、誰かの言葉を借りるなら、「誰も寝てはならぬ」だ。この感情が薄れて溶けて消えるその時まで、その目を閉じることは許さない。その目に映る自分の姿が小さくなって消えるまで、その目を逸らすことは許さない。
結局、あのお姫様は名前を暴けたのか? ――結末は誰もが知ってる。