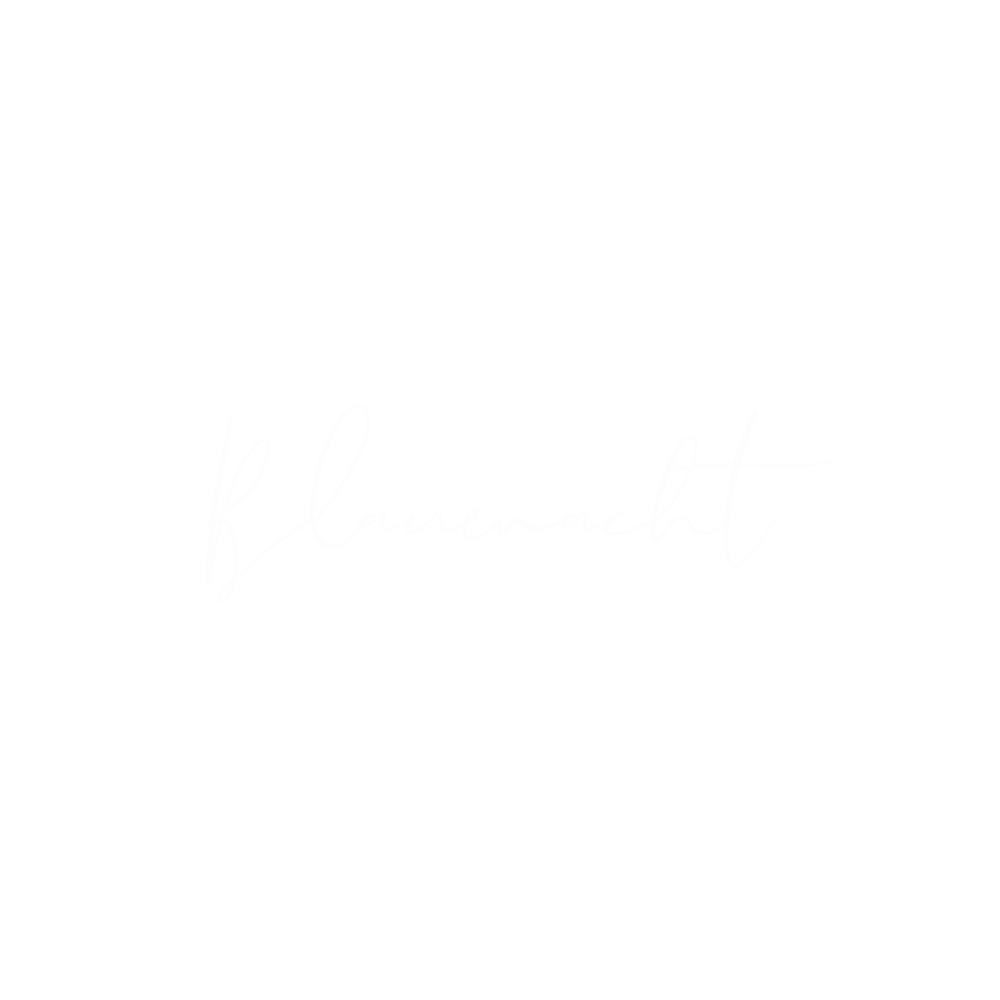十六番目の審神者 1
歌さに長編の冒頭。固定夢主前提ですが夢主の名前は出ません。
夢主=審神者=幼女。
この話以外も含め、うちのとうらぶ世界観はこういう感じ、という説明みたいな文章でもあります。
西暦二二〇五年。時の政府は歴史改変を目論む輩への対抗手段として、審神者なる者を見出した。とはいえ、ゼロから一度に百を目指すことはできない。そこで政府の役人たちは、国中の戸籍をあたり、素性や能力を調べ尽くして、三十人を選出した。最初の審神者たちである。
まずここから三年は試行期間だ。前例も何もないなか、言うなれば被験者として集められたこの三十人を足掛かりに、制度及びシステムの構築・改良、さらなる審神者の増加を目指すこととなった。
「立派にお勤めを果たすんですよ」
少女の母は厳しい人で、少女が審神者として政府に呼び出された時にも優しい言葉はくれなかった。もともと神職の家系だ。神様に失礼のないよう、徹底的に作法や振る舞いは躾けられてきた。その上常人を遥かに超える霊力を有しているのだから、審神者に選ばれるのも道理だった。齢わずか七歳。選び抜かれた三十人の中でも最年少である。
そんな少女を、両親をはじめ親族は心配するどころか喜んで政府に譲り渡した。審神者なる者が果たすべき命を聞かされたからだ。
曰く、刀剣の付喪神を顕現させ、歴史を変えようとする者を阻止するのだ。これは少女の家にとって願ってもない機会だった。また、少女には同等の霊力を持った兄がいたのだが、付喪神が男性の姿をしていると聞いた親族は、一も二もなく”捧げ物”を少女に決めた。付喪神とはいえ神を顕現させ、それらと生活を共にするというのなら、少女は神に見初められることもあるのではないか——ゆくゆくは神の子を授かることができるのではないか。それは家の名を押し上げて余りある名誉だ。
さすがに、わずか七歳の少女に面と向かってこれを言う者は居なかったが、聡い子だ、少女は幼いながらも大人たちの思惑を薄らと感じ取っていた。
霞ヶ関に立ち並ぶ省庁のビル、そのうちの一部屋に集められた三十人の最初の審神者たちは、この四月に新設されたのだという「歴史改変対策室」——文部科学省の中の一部門だそうで、政府としては、この問題は戦うことではなく「歴史」に重きを置いたということなのだろう——から、これからの自らの役割について説明を受けた。
一、一振りの刀を自ら選ぶこと。
一、選んだ刀の力を励起させ、刀剣男士を顕現させること。
一、自らに与えられた空間に、本丸を構築すること。
一、その本丸を維持し、また発展させること。
一、できるだけ多くの刀剣男士を顕現させ、戦力の増強を図ること。
一、政府の命により、刀剣男士を過去に送り込み、歴史遡行軍を倒すこと。
説明には一時間もかからなかった。ほんの一時間足らずで、審神者たちはこれからの人生を規定されたのだ。
前から順に、審神者たちは自分の最初の刀を選ぶために別室に呼ばれていく。
そんな中、少女は表情も変えず礼儀正しく与えられた席に座っていた。三十人の中に幼い彼女がいたからだろう、担当官はわかりやすい言葉ですべきことを説明してくれた。その中には、真名を明かしてはならない、というものもあった。刀剣男士は格はどうあれ神であり、名前を知られればたちどころに魂が囚われてしまうのだという。だから政府は、審神者のことを番号で呼ぶことにしたのだそうだ。そして少女に与えられたのが、「十六」という数字。
それを見て、少女に話しかける者がいた。
「こんにちは。ひとり?」
「十七」のネームプレートをつけた、十代半ばの女性だった。
「はい。私の役目だって、言われたので」
少女は表情を変えないまま、透き通る声で答えた。
少女の硬質な紫水晶のような瞳が、十七番審神者を見つめる。十七番審神者はその様子に、さすがにこの年齢で選ばれるだけのことはあると感心した。
「すごいね、わたし、上手くやれるか不安だらけだわ。お互い、頼りあって頑張ろうね」
見るからに華奢なその十七番審神者は、柔和に微笑んで言った。その微笑みにつられたのか、少女の硬質な瞳が微かに揺れる。
「はい。よろしくお願いいたします」
しかし少女はそれをすぐに瞳の奥にしまい込むと、変わらず硬く澄んだ声で答え、丁寧にお辞儀をした。
「十六番の方」
少女が頭をあげると同時に、番号が呼ばれた。はっとしたように、紫水晶の瞳が見開かれる。ちらりと十七番審神者を見やると、すぐに少女は表情を消し、しかし足早に部屋を出て行った。
十七番審神者も一気に緊張の度合いを増す。次は自分の番なのだ。しかし、去り際に少女が寄越した視線が忘れられない。少女の瞳は不安に震えていた。あの強くて硬い光を灯す瞳が震えていたのだ。どんなに優れた力を持っていると言ってもまだほんの子どもなのだと気付いた瞬間だった。