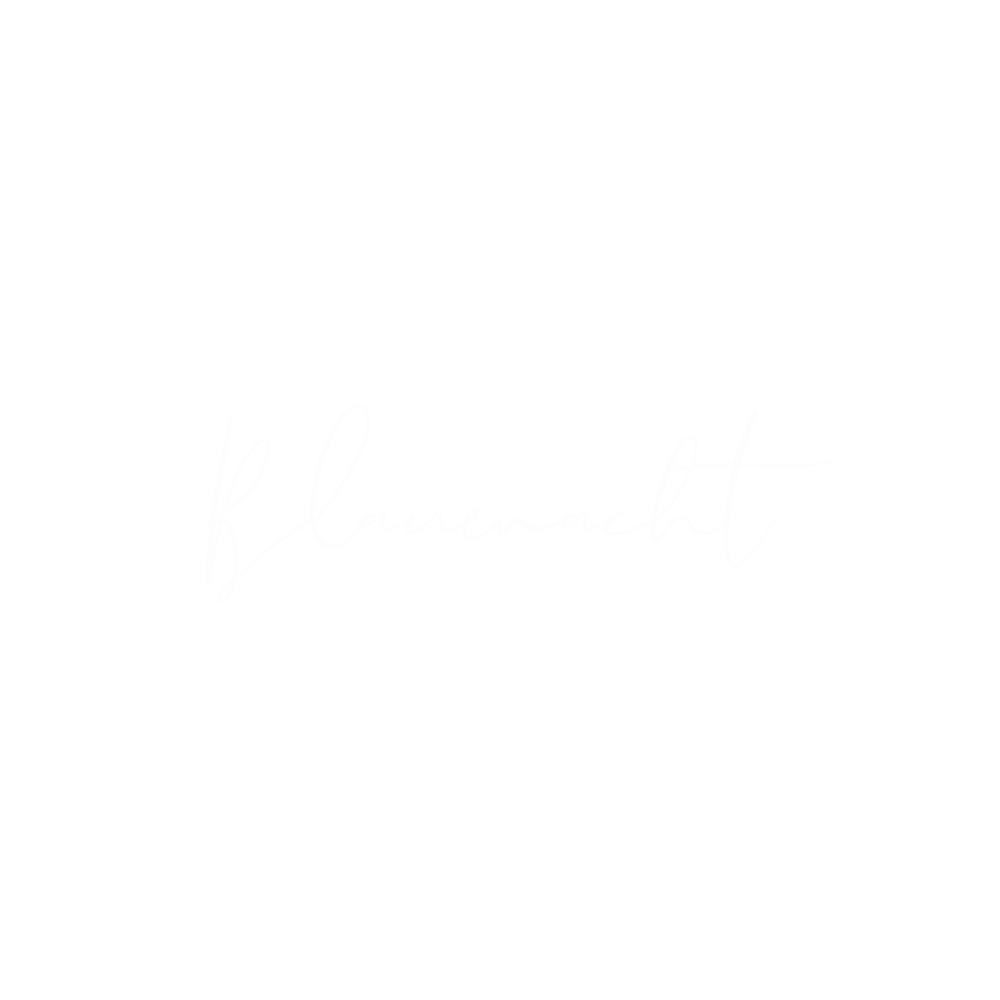歌仙兼定と出会う
固定夢主ですが夢主=審神者の名前は出ません。
初期刀の歌仙と出会う話。
わずか七歳の少女には、打刀は重かった。
刀を見るのは初めてではない。家であった神社には、祀られているというほどではなかったにせよ、氏子から寄贈された刀がいくつか保管されていた。危ないからと触らせてもらったことはなかったが、今、彼女が持っているものと、そう変わりはなかったはずだ。
「刀の神様が宿っている」と聞いていたので、彼女は小さな体には重いであろうその打刀、歌仙兼定を、捧げ持つように両手で抱えていた。他の審神者たちが自らの初期刀を小脇に抱えたり、担いだりするのを尻目に、彼女はその姿勢を崩さない。
敬うべきものの扱い方や、それに付随する所作は家で叩き込まれていたからだ。
「あなたが、僕の主かい」
どこからともなく舞った桜が消えると、美しく通る声で名乗った刀の付喪神――歌仙兼定は少しばかり目を見張った。
自分の目の前にいるのが、まだ幼い少女だったからだ。しかし自分の中に流れる霊力が告げている。自分を顕現させたのは、他でもないこの少女だ。
それだけではない。この少女の霊力が潤沢で、しかも清廉であり質も良いということまで、歌仙にはすぐにわかってしまった。
そして、主か、と問われた少女は、一瞬その言葉の意味を考え、そして答えた。感情の乗らない、平坦な声だった。
「あるじ……はい、そうです」
「なんと呼ぶのが良いのかな、もちろん、主とも呼ぶのだけれど。呼び名がないことには不都合もあるだろうから」
「呼び名……えっと……私の名前……」
予想もしないことを聞かれた、とでも言うように、硬く閉じられた感情と表情が揺らぐ。その拍子に、これまでは普通に名乗っていた自身の名を口に出しそうになり、慌てて歌仙に止められた。
しかしそれで少女は落ち着きを取り戻したようだ。一度口を閉ざし、すうと息を吸い、吐く。その頃にはすでに、先程と同じく硬い鉱物のような印象が、彼女を覆っている。
「失礼いたしました。政府の方にも、名を出さぬようにと言われていました。ええと……では、十六番とお呼びください」
「じゅうろくばん?」
「はい、十六番です。私、十六番目の審神者だって言われたので……」
相変わらず感情の籠らない声で少女は言う。語尾が薄れたのは、十六番と呼ばれるのが嫌なのではなく、目の前にいる神様がその柳眉をしかめたからだ。
「――つまり、政府はきみを番号で呼ぶのかい。……全くもって、雅さの欠片もない。十六……じゅうろく……そうだねえ、では、僕はこれからきみを『十六夜』と呼ぶことにしようか」
「いざよい……?」
「じゅうろくや、と書いていざよい、と読むんだよ。十五夜は知っているね? 十六夜月は、その十五夜を一日だけ過ぎて、ほんの少し欠けた月のことだ。あまり意味に違いはないかもしれないけれど、ただの番号よりは名前として相応しいのではないかな」
「いざよい、十六夜。――はい、こちらの方が好きです。歌仙兼定様、ありがとうございます」
どこまでも歌仙を上位とする姿勢を、つまりよそよそしい態度を崩さない少女――十六夜に、歌仙は苦笑しながら続ける。
「十六夜月というのはね、十五夜と比べると少し後に登ってくるのさ。なかなか出てこない月を、人はいざよう、と表現した。ああ、いざようというのは、ためらうというような意味だね。きみのその奥ゆかしさや慎ましさも、十六夜という名によく合っていると僕は思うよ」
歌仙の――神様の気分を害さぬよう、慎重に言葉を選び、ことさらゆっくりと言葉を紡ぐ十六夜は、それを聞いて少し困ったように眉を下げる。そもそも口数の少ない子どものようだ。だからこそ、今しがた顕現したばかりで右も左も、自分自身の体のことすら掴みきれていない歌仙が、こんなにも饒舌にならざるを得ないのだ。
彼はわからないなりに気付いていた。
この子はまだ幼く、庇護されるべき存在であると。そして、今ここでその役割を担えるのが、自分しかいないのだと。
十六夜は、たった今決まった自分の呼び名――これがそのまま、彼女の審神者としての名となった――の由来を注意深く聞いて、ゆっくりと飲み込み、その硬質な印象を与える藤紫色の瞳を少しだけ、和らげた。
「よろしく、十六夜月の君」