秋の足音

【企画参加】ミラニキお茶会しましょ
りぃさま(@rii_nikki_2 )の企画「ミラニキお茶会しましょ」に参加させていただいたもの。

prev | next

りぃさま(@rii_nikki_2 )の企画「ミラニキお茶会しましょ」に参加させていただいたもの。

prev | next
路地の奥から、金色の光がほんのり漏れていて雨上がりの濡れた石畳を照らしている。普段なら入らない、否、目に留まることもない細い路地だというのに、なぜだかミーシャはその金色に惹かれた。
〈骨董・古美術 天蓋臥榻〉
優美に曲がりくねった文字で書かれた店の名。その横のショーウィンドウから、金色の光は漏れている。
揺らめく光に誘われて、ミーシャはショーウィンドウを覗き込む。そこに広がっていたのはあまりにも美しい一つの、完成された世界だった。
異国を思わせる意匠の小部屋、色とりどりの玻璃のランプの柔らかな光が、繊細な陰影を描き出している。
その中央に少女はいた。
宝石箱のような椅子に腰掛けた人形。ミーシャは一瞬で心を奪われた。
水のように流れる繊細な衣服を身に纏った肌は本物の人のように艶めいていて、金色から段々と暗く青く変じていく長い髪は緩いウェーブを描いて肩や背を落ちる。
それだけでも息を呑む美しさだというのに。
きっと、彼女を作った人形師は、技術と情熱の全てを彼女の表情に込めたのだ。
ふわりと閉じられた両眼を縁取る長い睫毛。あどけなく、それでいて優美に少しだけ開かれた唇。幸せな夢を見ているのだろう、目元や唇に少しづつ薄紅色が差してある様は狂おしいほどの色香を漂わせながらも決して上品さや無垢さを損なうものではない。
そこに差すランプの柔らかな光。玻璃の反射を受けて、刻一刻と彼女の顔の陰影は移り変わり、様々な表情を浮かび上がらせる。髪や服も同じようにランプの光にきらきらと煌めいていて、それがさらに宝石となって彼女を飾っている。
飾られた花々も、眠る人形も、一つとして本当に生きているものはないというのに、それらは、その小部屋は、あまりにも生き生きとしすぎている。同時に、あまりに美しくあまりに緻密にすぎて、それ故に全く生を感じさせない静謐な場所でもあった。
どれだけの時間、立ち竦むようにショーウィンドウを眺めていただろう。
ミーシャは夢から覚めるように瞬いて、自分が細い路地に立っていることを思い出した。
まだ夢を見ているように溜息を零す。
「ジェマ」
傍に控える侍女を呼んだ。「店主に伝えて。
私、あの子が欲しいわ。」

誇魔さま(@oSQUAA3p2d2IFj2)の企画「人工天使計画」に参加したものです。
「智天使……!」
クレアは思わず叫んだ。
培養槽から姿を現したのは、紛れもない4枚羽を持った天使。こんなに高位の天使を作り出せたとあっては、叫ばない方がおかしい。
人柱となった少女は、世界を慈悲で包みたいと言っていた。海のように深い愛がいい、と。
なるほど、生まれた天使は水をそのまま衣にしたような衣服を纏っている。耳の奥で波の音すら聞こえたような気がするほどだ。
カシャン、とどこかでガラスが割れる音がした。直後、禍々しい空気が流れ込む。ああ、あちらは失敗したらしい。
すると天使の視線が動いた。視線の先には、失敗作。天使になり損なった何かが瘴気をばらまいている。
つう、と、水が流れるような動作で天使が腕を上げる。掌を失敗作に向け、握るように動かして——パシャ、というなんとも軽い音とともに、失敗作が水に還った。水はそのまま流れ動き、クレアの目の前に浮かぶ天使の衣の一部となった。
瘴気ごと、存在を消し去ってしまった。
強大な、強大すぎる力を目の当たりにして、クレアは総毛立つ。
彼女は、海だ。全ての母であり、全てを飲み込む海。
「慈悲深い」眼差しがクレアをひたと見据える。その感情は読めない。いや、そもそも人ではないのだ、感情があるのかどうかもわからない。あったとして、それは人の理解の及ぶものなのだろうか。
願わくば、「彼女」の思う慈悲と、我々人間が思う慈悲とが同じでありますように—— 彼女らしくもなく、クレアは神に——天使よりも高位の存在であるはずのものに祈った。祈ることしか、できなかった。


「あなたは私たちの天使」
両親にはずっと、そう言われてきた。遅く授かった子だからと、私にエンジェル、と名を付けた。
それが、いつからだろう。パパとママは、私をみんなの天使にしたがるようになったのは。
そんな2人が人工天使計画、というのを聞きつけてくるのは当然だった。私は嫌だって言ったのに。私はパパとママだけの天使でいられたらそれでよかったのに。
パパもママも、聞いてはくれなかった。
「本物の天使になれるのよ!」
だって。私、本物じゃなかったみたい。
器械につながれて、変な味のする薬も飲んだ。
もう声は出ない。多分、出せないようにされたんだと思う。だって天使になるための「試験」、痛いんだもの。
昨日も痛かった。今日はもっと痛かった。明日はもっと痛いんだろうな。
痛い、痛いよ。パパ、ママ、痛いの。
痛い、痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛——憎い
私の名前はエンジェル。
この恨み、どうやったら晴らせるかなあ?


自分の企画「溢れる雫を宝石に」に自分で参加したもの。
あなたのことを想うたび、私の体は重くなって、あんなに軽かった身体も、もう飛べなくなってしまった。
胸も息も苦しくて、こんなにも重いのに——それでもこの想いはこんなにも愛おしい。
零れる。
あなたを想うと、涙が止まらないの。
溢れる。
行き場をなくした感情は、ぽろり、ぽろりと転げて光る。
——毀れる。
重くて石のようになった私の体。溢れる想いが内側から私を毀つ。
重くて膝をついたら、そこから体が割れてしまった。そこから覗くのはきらきらひかる想いの結晶。
あなたへの想いが募るほど、私は罅割れ欠けてゆく。
こうやって、想いだけが残るのね。
最期の涙は、きっと一番綺麗な宝石になるでしょう。
私だってわからなくてもいい。あなたの元に、届きますように——

この冬は暖かかった。
森は毎年のように雪と氷で閉ざされ、凍えるほどの寒さだったというのに、彼女に逢えるというだけで、私の心は春のように暖かかったのだ。
それは私にとっても彼女にとっても初めての感情だった。殆ど触れ合うことはなく、交わしたのは心だけ。それでも私たちは満たされていた。
森の奥の古木、幾度も逢瀬を重ねた場所に、彼女が現れなくなったのはいつからだろう。
遺されていたのは、光を受けて輝く宝石の破片。
彼女の瞳の色をした、済んだ宝石の欠片だった。
私に出会わなければ、あなたは今も、あの美しい翅で舞っていたのだろうか。
あなたに出会わなければ、私は今も、こんな悲哀を知らずに過ごせていたのだろうか。
この冬最後の雪は、積もらず溶けて消えるだろう。
春はもうすぐそこまで来ている。
あなたを喪ったというのに、世界は変わらず芽吹いていくのだ——

さあ、行こうか。私の鵲に付いておいで。ああ、私をただのふらふら遊んでいる貴族の道楽息子だと思っていたのかい、まあそう見えているならそれでいいさ。

まあ、弟は馬車もご用意しませんでしたの?それは失礼をいたしました……よろしければ、わたくしの馬車で一緒に参りませんか。

鵲が群れをなして飛んだ。
隠せ、隠せ。子らを隠せ。
今夜は誰も外へ出るな。
森から災厄がやって来る。
森から這い出るソレは、うら若き乙女の姿をした化け物だ。
左手にて光を放つは真紅。
――獲物の顔を確かめる洋燈。
右手にて光を映すは月白。
――獲物の命を攫いとる大鎌。
灯を消せ。
見つからぬよう、息を殺して暁を待て。
我らにできるのはそれだけだ。

昼を夜に。
光を闇に。
凄絶な美を誇る、彼女は夜の番人。
生を死に。
全を悪に。
濃厚な死を纏う、彼女は刃の番人。
美しい氷の花を見たら気をつけなさい。
それは彼女の徴。彼女の司る処刑場の扉が開く場所。
何人も、彼女から逃れられはしない。
恐怖に震え、絶望に沈みながら、今夜も不運な贄が扉へと引きずり込まれてゆく。

ありがとう。今年も帰ってこさせてくれて。お祭り、一緒に行けて楽しかったよ。
ありがとう。道に迷わないよう、こんなにたくさん灯をともしてくれて。また来年、帰ってくるからね。
さようなら、元気でいてね。

あの人は、ここにいれば安全だから、と私を閉じ込めて行ってしまった。この美しさしかない静寂の場所に。
——貴方と一緒なら、どんな場所でも辛くなんてなかったのに。

君はきっと、閉じ込めたことを怒るだろう。君はそういう人だ。
戻ったらいくらでも怒られよう。
ただ僕は、どんなことをしてでも君にこんな光景を見せたくなかったんだ。

しゃら、とかすかな鈴の音がした。
一瞬ざわめきが起こり、しかし店内はすぐに水を打ったように静まり返る。
しゃらん
少し近づいた鈴の音に耳を澄ます。
もしかして、彼女なのだろうか?
ー・ー・ー・ー・ー
街の奥、喧騒を抜けた先にその店はある。
どうということのない、どちらかというと古びて胡散臭い部類に入るような店だ。
外から見ただけではわからないが、店の中庭には静かな池と古い古い橋があって——
夜にだけ、舞姫が現れる。
彼女は気まぐれに現れて橋の上を舞う。来るたびに彼女の舞姿を見られる人もいれば、何度訪れてもその気まぐれに当たらない人もいる。
その、彼女が。
月の光から浮き上がるように、鈴の音を纏って現れた。
しゃらん、彼女が身につけた鈴が歌う。
顔を隠した扇の隙間から、かすかに微笑む唇が覗く。
それだけで恐ろしいほどの美しさだ。
しゃらん、彼女のヴェールがふわりと広がる。
とんでもなく優雅に、彼女は扇を翻す。
瞬間、僕は彼女に心を奪われた。
宝石のように、月光を受けて煌めく真紅の瞳が、僕を見つめて少し細められる。
この上もなく美しい唇が、く、と弧を描く。
時間がとろりと揺蕩って、全ての瞬間がスローモーションのように見えた。
彼女の銀色の髪が彼女の動きに合わせて散らばり、細く美しい指が池の水面をつう、と撫ぜ。
その全てを、僕は恍惚として見つめていた。

魔女といえども、時代の流れには逆らえないさ。だがなに、電子演算というのも慣れてみれば便利なものよな?

光は甘美な闇にどうしようもなく魅せられ
闇は高貴な光にどうしようもなく焦がれる
わたしたちは魂の双子。
魂で惹かれ合うわたしたちを、誰が分かつことなどできようか?


生垣の隙間をなんとかくぐり抜け、ようやく仔羊を捕まえた少女は息を飲んだ。ここはあの花屋敷だ。魔女が棲むと言われるあの屋敷。
と、窓が開いたかと思うと、そこから顔が覗き——少女と目が合った。
美しい人だった。陽の光のようなの髪、冬の晴空のような瞳、そして、大きな翼。
「天使さま……?」
思わず見惚れた少女は、知らず知らずに呟いていた。
天使は微笑むと、他の人には内緒だよ、と言うように唇に指をあてた。
✳︎✳︎✳︎
夢見心地で牧場に戻った少女は、仔羊の首輪に何か挟まっているのに気づいた。
キラキラと光る、それはあの羽根だった。


さあ!どれでも好きなのを食べて頂戴。
ここにあるのは夢のキャンディ。
食べたキャンディの夢を見られるの。素敵でしょ?
馬の形?夢の中ではロビンソン・クルーソーになれるかも!
あなたが選ぶのは薔薇の花びら?素敵な恋のヒロインを楽しんで。
鳥になって空を舞うのも楽しいわ。
同じ空を舞う夢でも、蝶ならもっと優雅かも。
星型を食べたら、目覚めたあなたは元気一杯。
あら、宝石のキャンディが気になるの?
これはとっておき、あなたの望む夢を見せてくれるわ。
あなたの夢はあなたの秘密。
夢では自由になっていいの!

みるくさま(@ilovedogs_xxx )の企画「それでも貴方に会いたい」に参加させていただいたもの。
歩いて、歩いて。時を超え幾星霜、歩き続けて。
荊に引き裂かれようと、誰も私を覚えていなくても、貴方に会う、ただそれだけのために私は歩き続ける——

外の世界は怖いから。
——私は私の世界があればいい。

さあ、あなたのお名前は?
名簿にあれば通って良し。
名簿に無ければ、残念だけど、徳を積んだらまた来てね。

アリアさま( @yur_305 )の企画「闇に染まる物語」に参加させていただいたもの。
ヴェールの下は女の素顔。
貴方以外には見せられないわ。
私の全てを受け入れられる、
特別な貴方以外には
決して、誰にも見せないの。

嵐の夜には、美しい人に化けた妖が出るっておばあちゃんが言ってた。眼鏡でもガラスの破片でも何でもいいから、それを通して見れば本当に人かどうかわかるらしいけど…どういうことだろう?

あーあ、たーいーくーつー!
あっ、でもだんだんあったかくなってきたね。さっきちょっと寒かったから街燃やしてきちゃった!

町外れにすごく綺麗な庭のあるお屋敷で最近見かけるあのメイドさんのことが頭から離れない。この辺りでは見ない顔立ち、真っ黒で艶やかな髪。きっと異国から来たんだろう。どんな風に笑うんだろう?あの細い指に触れられたら、どんなに幸せだろうか——

ああ、ああ、ああ——やっと巡り逢えた!
私の愛しい人、もう決して離れない。
私の愛しいあなた、もう決して離さない。
わたしのあなた——

何不自由なく、何の苦痛もなく、ここにいれば、永劫貴方は満たされる、そうでしょう?
さあ、私と一緒に、時の終わりまで——

またお前に会えるなんて。
お前のいない旅は退屈でたまらなかったんだ。
ありがとう、また私を見つけてくれて。
さあ、世界を征こう。お前となら、きっとまた楽しい旅になる。お前と私の2人なら、できないことなどないはずだ。

やっと来たか。待ちくたびれたぞ。
酒もある。貴様と死合うて百余年、貴様と語り合う日を待ち望んでいた。
そう睨むな、まだあの時のことが悔しいか?私が貴様に止めを刺した、あの時が。

たとえ我が身は闇に堕ち果てようと。
我が愛しき記憶は何人にも穢されぬ。

善なるわたしの、キタナイ心。
不要なものだとわかっているのに、捨て切れなかったわたしの心。
鍵をかけて閉じ込めて、わたしの奥に眠らせておくわ。

旅立ちは残酷で。
籠の中は暖かくて、甘くて、幸せ。それでもいつかはここから出なきゃいけないって、わかってはいたの。
だけど、まだ飛び方も知らないのに——
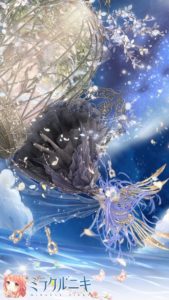
「だぁめ、見せてあーげない!」
くすり、少女は嗤う。
にっこりと笑みを作った顔の中、その瞳だけは冷たくて。
「それともなぁに?そんなにこの箱の中身が気になるの?」

鍵なんてかけたって無駄さ。”アレ”は夜になると、猫のようにいつの間にかするりと入り込んでいるんだ。
まあ、害があるわけじゃないんだが……いかんせん、家に得体の知れないものが入り込んでくるっていうのは少し不気味だよな。

たとえどんなに美しい世界でも、貴方がいないのなら意味なんてない。堕ちる先は、光という名の地獄。
この光り輝く世界で貴方を喪ったまま生きていくことが、私の罰。

悲しみも醜さも全部全部隠して、貴方に見せるのは一番きれいな私。

あの日切り捨てた、あの人の心のいちばん綺麗で柔らかな欠片。 静かに微睡みながら、全てが終わる時を夢に見て——

永い微睡みは暖かくて、明るくて。終わることなく繰り返す美しい思い出に憩うのは、あの日置き捨てた最後の光。

もうここに誰が眠っているのかなんて、誰も覚えていないし、私も知らないけれど。昔むかし、悲しいことがあったんだって聞いたから。お花を手向けるのは、良いことなんでしょう?

忘るるなかれ。
我らの物語が数多の屍の上に成り立っているということを。

父さんの残した古びた鍵を、古くて重そうなドアに差し込む。捻ると少し抵抗はあったが、すぐにカチリと音を立てて解錠される。
予想通り重い扉を押し開けると、きっと扉と連動していたんだろう、天窓の覆いが外れて一筋の月光が暗く埃っぽい部屋に差し込んだ。
その光の先で、かすかに時計の針が動くような音がして、それはすっくと立ち上がる。鋭利に尖った針で器用にバランスを取るガラス球だ。
ぎょっとしてそれを眺めていると、ガラス球の”奥”から、信じられないことに人(本当に?)が現れた。
「ああ——やっとか。待ったぞ、イーライ。次の行き先は決まっ、……ん?君、イーライではないな。……ふむ。一つ問うが、今は何年だ?」
問いを向けられた、らしい、というところまでは理解できたが、そもそもこのガラス球が理解できない。ガラスの中に人がいる——?
「おい、呆けているんじゃない。何だ?私が気になるのか?ふ、私は羅針盤だ。私は私の知識と計算によって道を示す。普通の羅針盤がこんな風ではないのは知っているが、目の前の現実を受け入れるんだな。私は今、君の前に存在している。」
濃紺のドレスに身を包んだ麗人が、僕に語りかけてくる。羅針盤、と聞いてぴんときた。日記にあった特別な羅針盤とは、このことじゃないのか。
「それでだ。もう一度問うぞ。今は何年だ?私は羅針盤、正確な情報がなければ何もできない。私に知識を与えてくれ。」
きっとそうだ。父さんの日記には「美人な上にその辺の男よりよほど勇敢」だとか「知識欲がすごい」だとか書かれていて、羅針盤なのにどういうことなのかと思っていたのだが、その意味がようやくわかった。
「今年は新暦783年。イーライは僕の父さんだよ。」
「ほう、783年。19年ぶりの世界か。それに、少年、イーライの子とは!あ奴も父になったのか。それは良い!君の名はなんというんだ?」
おもしろそうに目を細め、羅針盤はさらに問う。
「僕はユーリ。ええと…あなたは確か、リュミエールと言うんだっけ?」
「おお、よく知っていたな!そうとも、我が名はリュミエール。リュミエール・ド・シリュース。どんなに暗い道をも照らし出す星の光だ。」
名乗る羅針盤——リュミエールは誇らしげで、その瞳がきらきらと輝いたのがガラス越しにも見て取れた。
「ユーリ、君はなぜ今、私を目覚めさせたんだ?」
自己紹介と現状確認が済んだ後、本題だと言わんばかりにリュミエールは問うてくる。……特にあなたを目覚めさせようと思ってたわけでは、ないんどけど。
「ああ、いや……その、旅に、出たくて。父さんが、その時が来たらここを開けるように、って鍵をくれたんだ。」
「開けてみたら、私が目覚めた、と、そういうわけか。」
リュミエールはそれで全て察したようだ。——僕が口に出さなかった部分も含めて。確かに、状況の把握や判断はものすごく速くて的確だ。
「偶然にしろ、私を目覚めさせたのは正解だぞ、ユーリ。船があろうと操舵手がいようと、羅針盤がなければ旅には出られないのだから。船や人手は金があれば手に入るが、私はそうはいかない。」
「ちょ、っと待って、あなたは僕の旅について来てくれるの?」
「? 当たり前だろう、私は羅針盤だぞ?それとも何か、君は羅針盤もなしに旅立とうとしていたのか?」
「いえ、その……一緒に来てくれるのなら、とても嬉しい、です。」
それを聞くと得意げに鼻を鳴らし、リュミエールは旅装や持ち物についてのアドバイスをくれた。
「そういえばリュミエール、あなたは父さんのこと、聞かないんだね。」
「聞かずとも想像はつくさ。19年間も私を放っておいたのだし、いざその静寂を破ったのは奴の息子だった。とくればなおさら。」
僕の荷造りを見守っていたリュミエールは不敵な笑みを消し、遠くを見るように目を細めて続ける。
「イーライは好奇心の塊だった。いろんなものに興味が尽きず、だからひとところにとどまれるような男ではなかったよ。そうか、あのイーライが父になったのか……イーライはよほど君と君の母君を愛していたのだな。でなければ私をこんなに長い間放って身を固めるはずがない。そうかそうか、良いことだ……」
親しい友人を懐かしむような眼差しだった。
「父さんは、僕にたくさん若い頃の冒険の話をしてくれて…僕はそんな父さんに憧れたんだ。いつか僕も、父さんみたいに宙を駆けるんだって。
そう言ったら父さん、僕に日記とここの鍵をくれたんだよ。
使い古されたトランクに、アミュレット、最低限の着替え、それから何かの足しになるだろう、と引っ張り出した銃を放り込む。もちろん、父さんの日記も入れた。
航空図をまるめ、父さんが旅の途中で手に入れ、気に入ってずっと使っていたという旅行マントを羽織り——ささやかな荷造りは終了した。
もうすぐ夜明け、旅立ちの刻だ。
家の扉に鍵をかけ、その鍵を内ポケットの一番下にしまい込む。そして波止場までの道をじっくりと歩く。次に帰ってくるのはいつになるのか、僕にもわからない。だから、しっかり覚えておかないと。
リュミエールは、その全てを何も言わずに見守ってくれた。
波止場は静かで、僕が乗り込む予定の貨物船も、黒いけれども穏やかな波に浮かんでいる。
ゆくゆくは自分の船も欲しい。父さんの船を探すのも良いかもしれない。
「そういえば、父さんの日記には、羅針盤はとても大きくて、あなたと話すのに階段を使わなきゃいけなかったって」
ずっと黙っていたリュミエールに話しかける。
「ふふ、大きさの概念など大した問題ではないさ。イーライと旅していた時は、私は船の支柱でもあったからな。当然、ある程度の大きさが必要だった。しかし今は違う。君との旅はもっとコンパクトだ。合わせるとも。」
暗い海を背に、リュミエールは目を閉じた。ガラスの中にいるのに、まるで海からの風を感じているようだ。
静かな波の音しか聞こえない数瞬ののち、ふっと息を吐いたリュミエールは、煌めく宝石のような瞳を開くと僕を真っ直ぐに見つめた。
今こそその時だ、と言うように。
「さあ、準備はいいか、少年。イーライの息子ユーリよ。この世界には、あの男ですら見つけ出せなかった神秘がまだまだ眠っている。いざ征かん、さらなる未知を求めて!」
リュミエールの高らかな宣言とともに、夜明けの最初の光が旅立つ僕らに向けて差し込んだ。
新しい日が、新しい旅路が、始まる。

イーライ(イライアス)はユーリの生まれる2年前に結婚、リュミエールの元を離れた。ユーリは17歳。
宙を夢見て、故郷を飛び出して。なけなしのお金はすぐに尽きて、でも運良く探検家だという人に拾われて、今に至る。
僕も探検家になりたいんだと言ったら、彼は豪快に笑って、後に何も残してきていないのなら、それなら一緒に来るかと誘ってくれた。
星の海を行く船長は、決して道を間違えない。
それは、彼女がいるからだ。
彼女というのは、人ではなく(人のように見えるが、おそらく違うのだろう)、何か偉大な存在が作り上げたに違いない”羅針盤”のことだ。
彼女は船の中心、一番見通しの良い場所に置かれていて、その部屋の天井と壁は広く星々が見渡せるようガラス張りになっている。
拾われて最初の日、船長は僕を彼女に引き合わせた。
「やあ、”羅針盤”。調子はどうだい。新入りの紹介だ。こいつはイーライ。つい今しがた、うちの仲間になったんだ。良くしてやってくれ。」
船長はそれだけ言うとあとはお前次第だ、と言うように僕の肩を叩くと操舵室へと戻ってしまった。
——ガラスで隔たれているにも関わらず、彼女は圧倒的なオーラを放っている。
思わず立ち竦むと、その人は不敵な笑みを浮かべて僕を見下ろした。
「さあほら、そんなところにいないでその階段を上がっておいで。それは、私と話をするための階段なんだ。」
深く、耳に心地よいアルトが僕に話しかける。
「イーライと言ったな、どうした。私が恐ろしいか?それとも、旅路が不安か?」
正直、どちらもだった。そしてそれはすぐに、彼女にも見透かされてしまったらしい。
恐る恐る階段を上ると、真正面からその人と目が合った。
宝石のようにきらきらと輝くその瞳は、おもしろいものを見つけたと言わんばかりに僕を観察していて、けれどもそれだけではなく深い深い叡智を感じさせた。
「まずは自己紹介だな。私はこの船の羅針盤。それが私の意義であり名前だ。私のドレスを見てみろ、たくさん計器がついているだろう?これと、このガラス球の中にある道具全てを使って、この船の進路を割り出すんだ。
それで、君は?名前からもう一度聞かせてくれ。船長も言っていたが、君の口から聞きたい。」
彼女は自信に満ち溢れていて、僕はというと未だに彼女に圧倒されてはいたけれど、彼女の声や瞳に脅かすような色はなく、単純に新入りを知ろうとする先輩、といった風だったので幾分安心した。それに、意地の悪い人ではない、というのは直感的に感じ取れた。
「はい。僕はイーライ。今朝、船長に拾われたんです。……」
どうしよう、もう話すことがない。僕は別に、何かを成し遂げて来たわけでもないんだ。
「ほう。それでイーライ、なぜ拾われたんだ?」
「それは……」
「誇れるような理由ではないのだな?大丈夫、あの男が拾ったんだ、そのことに価値がある。お前はあの船長にとって拾うに値する男だったということだ。
まあそもそも、拾う、というあたりからして、身一つで宙へ上がったが諸々が尽き果てた、といったところか。」
「……はい。」
さすがの思考処理能力と言うべきだろうか。僕のことなんてお見通しみたいだ。
「恥じることはない。身一つでも宙へ上がろうという気概があるのだから。それ程までに宙に惹かれたのだろう?探検家というものは得てしてそういう人種だし、そうでなければ面白くない!
良いだろう、この”羅針盤”、君を歓迎しよう。さあ、ガラスに手を当ててくれ。握手の代わりだ。」
そう言うと”羅針盤”はガラスで隔たれた僕の前に手を差し出した。それに合わせるように僕もガラスに手を当てる。
冷たいガラスは触れた彼女の体温で温まっていて、確実に温もりを僕に伝えてくれた。
僕の掌も、そうやって彼女に伝わっているんだろうか。
「そういえば……あなたには”羅針盤”以外の呼び名はあるの?」
いくらか打ち解けた後、僕は彼女に問うた。すると彼女は怪訝そうな顔をして否定する。
「いいや、無いが?それがどうした。私は羅針盤で、それ以外の何者でも無いのだから。」
「それなら、あなたに名前をつけても良いかな?”羅針盤”、なんて、それは機能のことであってあなた自身の名じゃないよ。」
「ほう?なるほど、そう言われてみれば。
——良いだろう、私も他のちゃちな羅針盤と同じにされるのは嫌だったのだ。
だが心して選べよ、私にふさわしい名を与えておくれ。」
……もしかして、僕は今ものすごく大それた、しかも責任重大なことを言ってしまったのだろうか。一瞬後悔のようなものがよぎったものの、ここで断って彼女に幻滅されるのは嫌だった。
「じゃあ、少し時間をください。思いつきで適当な名前を付けるのは嫌だから。」
そこから、僕の悩みの日々が始まった。
そしてそれは、彼女がどれだけ優秀かを見せつけられる日々でもあった。
遠い星々の波を見、航路を計算し、時空の嵐を読み切る。彼女はまさに、世界に二つとない存在だった。
——その彼女に、僕なんかが名前を付けるだなんて。船長に相談しても、今までそんなことを誰も考えつかなかった、お前がやるべきだしお前にしかできないと言われてしまって。
なら、やってみるしかないじゃないか。
「リュミエール。リュミエール・ド・シリュース、というのはどうかな。最も明るい星の名前だよ。あなたは僕たちの光、先の見えない旅路を照らすたったひとつの光なんだから。」
たっぷり2週間。思えばずっと、それこそ寝ている時だって彼女と彼女の名のことを考えていた気がする。
そして最後に決めたのが、宙で最も明るい青い炎、知らない者など居ないあの星と、その光だ。あとは、彼女が気に入ってくれるかどうか、なんだけど。
「——リュミエールか。うん、悪くない。」
そう言うと羅針盤は何度かその名を反芻する。
「リュミエール・ド・シリュース、気に入った、実に良い名だ。君に感謝を。そして我が名にかけて誓おう。この先がどんなに暗い星々の影でも、どんなに深い迷いの海でも、我が叡智の光が君を導こう!」
彼女の誓いに呼応するように、ぶわりとリュミエールの髪がなびいた。ドレスの計器も輝きを増したようだ。どこからとなく青い鳥が舞って、彼女の肩に緩やかに着地した。
以来、”羅針盤”は船のみんなからリュミエールと呼ばれるようになり——というか、リュミエールがそう呼ばれないと気分を損ねた——晴れて僕も、リュミエールが認めたなら、と名実共にこの船に受け入れられた。
リュミエールがさらに張り切って力を発揮するようになったのは言うまでもない。
☆☆☆
さて、僕とリュミエールの出会いについてはここまでだ。ええと、なぜ今ごろになっていきなりこれを書こうと思ったんだったか。
ああそうだ、あの頃の僕はまだ日記を書いていなかったんだ。記録も兼ねて、これは書き残しておくべきだと思ったんだった。だってリュミエールとの出会いが僕の人生を変えたんだからね。
のちに僕は、船長からこの船とリュミエールを受け継いだんだが……それはまた別の物語だ。知りたいなら、僕の日記を読むといい。旅したことは全て書き記したからね。
新暦763年10月26日

コーデ画像はSSの元になった1つではありますが、実際にイーライなんかが登場するコーデはフォロワー様が組んでくださったものなので掲載はしておりません。
自分の企画「アーティフィシャル・エデン」に自分で参加したもの。
沢山のAIを作ってきた。量産型も、一つしかないものも、沢山。
彼女たちは今日も、この惑星を回すために尽力してくれている。
私が作るAIはこれで最後。この惑星のために何かを成すためでも、何かを守るためでもない。この子の役目は、私を看取ること。
そういえば、今まで私は、私のためのAIは作ったことがなかったんだわ。
だから今回は腕によりをかけた。私の思う美しさを全部詰め込んだの。
ホログラムだけれど、翼だってつけたわ。天使様に看取られるなんて、素敵でしょう?
「フィン」
もう大きな声は出せないから、口元に近づけたマイクでその名を呼ぶ。
終曲であり、繊細な美術品であるフィン。私の宝物。
呼べばフィンは静かに側に佇んで、手を差し伸べてくれる。
『マスター』
ああ、フィン。あなたは私の最後にして最高の傑作。
『マスター、笑っているのですか。』
そうよ、あなたが素晴らしくて誇らしくて、微笑まずにはいられないの。
でも、もうそろそろ時間ね。
機能を維持するために手術を重ね、外見だけは20代の頃のままだけど、私の体はもう限界。
「フィン、着替えを手伝って頂戴」
昔むかし、まだこの惑星ができて間もない頃の服が着たいの。私がここに移住する時に持ってきた、あの頃の服を。
『マスター、今日は上機嫌ですね。』
フィンはそう言って私を着替えさせてくれ、その後私を花で囲まれた椅子に座らせると満足そうな顔をした。
『お似合いですよ、マスター。次は何を?』
「そうね……では、そこに立ってあなたをよく見せて。それから、私のことも、見ていて、ね……」
力の入らなくなった体で、何とかフィンを見つめる。私が最期に見るものは、私が愛したものがいい。
『マスター?……マスター…!』
傾いだ私の身体を支えて、フィンが私を呼ぶ。ああ、フィン、私の天使。
あなたに抱かれて逝けるなんて、私はなんて幸せなんでしょう。アーティフィシャル・エデンは間違いなく楽園ね。
もう何も見えない。意識もゆるゆると闇に溶け込もうとした時、頬に何か雫が落ちるのを感じた。
『マスター、マスター。私を生んでくれて、ありがとう、ございました……』
フィン。私の天使。私の愛し子。
あなたを悲しませたくはなかった。
だけど、よかった。
——あなたは心を手に入れたのね。
安堵とともに、私は最期の息を吐き出した。


文坂日向さま(@Nikki_AyskHnt)の企画「魔法学園の学生」に参加したものです・
「あああ!また出てきちゃった!」
振り返って叫んだのはシャルロッテ、今年この学園に入学したばかりの1年生だ。足元にはぽんぽんと花が咲き蔓が伸びている。彼女の一族は代々森を守る役目を負っており、だから皆今のシャルロッテのような草花を生やしたり育てたりといった魔法を生まれた時から備えている。ただ——シャルロッテは少しその力が強いらしい。彼女の意思に関係なく、彼女が歩けば草花が育ち、彼女がくしゃみをすれば花びらが舞う。これではさすがに日常生活にも支障が出るからと、この学園で魔力の制御を学ぶことになったのだ。
「ねえ、ジーン、こういう時どうすればいいんだっけ!」
焦ったシャルロッテは肩にとまっている青い鳥に尋ねる。故郷の森からついてきてくれた使い魔だ——といってもシャルロッテよりよほど知識のある妖精なのだが。ピピ、とジーンはシャルロッテに囀りかける。
『ほら、まず落ち着いて。それから魔道書を開く。2週間前に習ったはずだよ、さあ。』
特に魔法のアドバイスというわけでもなかったが、その言葉に落ち着きを取り戻したシャルロッテはコホンと咳払いをすると、魔道書のページを開いて杖を構えたのだった。

『フロリア、君も人が悪い。わざわざ私を可視化させる必要はなかっただろう?』「そうねえ、でも、その方が効果的だったでしょ。」
フロリア・アイデン先輩。品行方正、成績優秀、優しくて綺麗な、みんなの憧れの先輩。先生たちの間でも、首席卒業はフロリア先輩だってもっぱらの噂。でも誰も、先輩の魔法がどんなものか知らないの。
夜、誰も居ないはずの講堂に青い光が見えた。気になってしまって寮から抜け出して覗き込んだ講堂に浮かんでいたのは——
(月……?)
どうして屋内に月があるのか、とさらに足を踏み入れ近づくと、人の影がぼんやりと見えてきた。と、その時。その人の足元に魔法陣が浮かび上がり、上に立っているその人のベールがばさりと翻って顔が露わになる。
誰なのか分かってしまった驚きは、でもすぐに恐怖に変わってしまった。魔法陣から不気味な青い灯火がたくさん出現して、さらには骸骨の手みたいものまで這い出して来ようとしている。思わず後ずさったら、扉にぶつかって派手な音を立てながら尻餅をついてしまって。その人——フロリア先輩が少し驚いたような顔でこちらを振り向いた。
「あら……見られちゃった?」
先輩は驚いた顔をすぐに笑顔に変えて私に話しかける。
「大丈夫、怖いことなんてないわ。腕が鈍るから練習してただけ。怪我はしてない?」
先輩は勝手に覗き見して勝手に転んだ私の心配をしてくれる。私は私で、いつもの先輩の声を聞いて安心したのかさっきより怖さもましになってきた。
「ごめんなさいね、怖がらせてしまって。私の家はね、死霊魔術の家系なの。でも、死霊魔術って印象が悪いでしょう?だから学園では隠してるの。」
先輩が私の手を取って立ち上がらせてくれる。ありがとうございます、とお礼を言おうと先輩を見上げて——また私は腰を抜かしそうになった。骸骨だ。先輩を後ろから抱きしめるように浮かんでいる。声も出せず固まった私をみて、先輩はもう一度優しく微笑んだ。
「ああ、彼は私の使い魔。取って食べたりはしないわ。ねえ、私、私が死霊魔術師だって学園の人たちに知られたくないの。今日見たことは、誰にも言わないでね。約束よ?」
無言で頷くしかなかった。私は講堂の入り口まで付き添ってくれた先輩にそそくさと礼をして、逃げるように自分の部屋にたどり着くとベッドに潜り込んだ。
